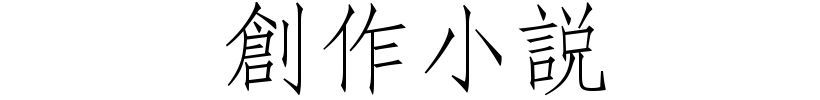萩子は、自分の流す涙の量に驚いている。
次から次へと、ぽろぽろ溢れてくる。
少し心配になる。
生物の時間を思い出した。人体は、ほとんど水でできている。
私は、それを実証しているわけか。
可笑しくなる。
でも、別れようという言葉は、あまりにも悲しすぎる。
萩子は、窓ガラスに映る自分を、しばらく眺めた。
コーヒーの香りに、初めて気付く。
明るく気持のいい陽光に満ち満ちた夏が終わり、秋が訪れる。
夏が終わろうとする時、人は、あれほどにも元気だった陽光が、弱々しさをみせるのを見て、不安になる。
光りが漲っていた空は、暗い雲に覆われる。しっとりとした雨が、降り続く。
人は、夏を恋しがる。
しかし、やがて雨に磨き抜かれたような、美しい秋が現われる。
そんな秋は、心に染み入るような美しさを持っている。
夏は思い出となり、人は、秋のどこか淋しげなきらめきを楽しむ。
萩子は、スケッチ・ブックを持って、砂浜に腰を下ろしている。
夏の賑わいが終わった、秋の海。
萩子は、その海を丹念にスケッチ・ブックの白の空間に写し取っていく。
人間は、海から生まれた。だから、ほとんど水分でできている。
あれから、何年たったんだろう。
萩子は、立ち上がる。
海風を感じた。
1995/09/21
2016/04/02
雨
空気は、湿って重い。
細かい雨が、降っている。
枝を四方に広げた大きな木。
根元に少年が、立っている。
少年は、木を見上げる。
少し前までは、陽光に緑を輝かせていたことを思う。
風が渡ると、さわさわと気持のいい音を聞かせてくれた。
いまは、葉の1枚1枚が、雨にしっとりと濡れ、軽快さを失っている。
少年は、そっと溜息を吐く。
会社に急ぐ人たち。
彼らも、白い輝きから、陰欝な暗い色に変わっている。
タバコの煙が、空中で軽く流されている。
水分をたっぷり吸い込んだアスファルトの道路を、自動車が、走る。
路面は、自動車の赤い光を反射させる。
少年は、木に視線を戻す。
木は、どう感じてるんだろう。
少年は、周囲を見渡す。それから、木の幹に軽く耳を当てた。
なにも聞こえない。
木が身じろぎした。
少年は、驚いて木を見上げる。
暗いグレーの空に広がった、枝。
何事もない。
どんと背中を叩かれる。
少年は、バランスを失い、2、3歩よろめく。
振り返ると、少女が、笑っている。
大きな口を開けて、ぼんやりしているなんて、ずいぶんみっともいいわね。
少年は、顔を赤らめる。
少し遅れてしまったわ。急ぎましょう。遅刻するわよ。
少女は、少年の手を引っ張る。
少年は、またよろめく。
木が笑った。
少年は、振り返って、木を見る。
なにしてるの、本当に遅れるわよ。
少女に手を引かれながらも、少年は、何度も振り返る。
とうとう少女は、怒ってしまう。少年を置いて、どんどん先に行く。
少年は、しばらく木を眺める。
それから、少女を追った。
1995/09/19
細かい雨が、降っている。
枝を四方に広げた大きな木。
根元に少年が、立っている。
少年は、木を見上げる。
少し前までは、陽光に緑を輝かせていたことを思う。
風が渡ると、さわさわと気持のいい音を聞かせてくれた。
いまは、葉の1枚1枚が、雨にしっとりと濡れ、軽快さを失っている。
少年は、そっと溜息を吐く。
会社に急ぐ人たち。
彼らも、白い輝きから、陰欝な暗い色に変わっている。
タバコの煙が、空中で軽く流されている。
水分をたっぷり吸い込んだアスファルトの道路を、自動車が、走る。
路面は、自動車の赤い光を反射させる。
少年は、木に視線を戻す。
木は、どう感じてるんだろう。
少年は、周囲を見渡す。それから、木の幹に軽く耳を当てた。
なにも聞こえない。
木が身じろぎした。
少年は、驚いて木を見上げる。
暗いグレーの空に広がった、枝。
何事もない。
どんと背中を叩かれる。
少年は、バランスを失い、2、3歩よろめく。
振り返ると、少女が、笑っている。
大きな口を開けて、ぼんやりしているなんて、ずいぶんみっともいいわね。
少年は、顔を赤らめる。
少し遅れてしまったわ。急ぎましょう。遅刻するわよ。
少女は、少年の手を引っ張る。
少年は、またよろめく。
木が笑った。
少年は、振り返って、木を見る。
なにしてるの、本当に遅れるわよ。
少女に手を引かれながらも、少年は、何度も振り返る。
とうとう少女は、怒ってしまう。少年を置いて、どんどん先に行く。
少年は、しばらく木を眺める。
それから、少女を追った。
1995/09/19
2016/03/29
愛
鍬の刃が、さくさくと気持ち良く土に中に入っていく。
太陽は、真上から照りつけているが、夏の激しさの変わりに、優しさを持っている。
老人の体は、軽く汗ばんでいる。風に冷たさを感じる。
見上げると、太陽は、西に傾いている。老人の長い影を、畑の上に作っている。
今日は、これまでだな。
老人は、腰を下ろし、タバコと携帯用の灰皿を取り出す。
タバコに火を点ける。タバコの煙が、夕焼けの空にゆっくりと昇っていく。
老人は、妻の身体を拭いていたとき、湯が天井に反射した、明るい陽光のことを思った。
あの光は、心を癒す光だ。
妻の背中には、大きな傷跡がある。
若い頃、老人の心は、荒れていた。
酔った老人は、恐ろしい勢いで妻を蹴飛ばした。その時の傷だった。
そんな老人を、妻は、なにも言わずにいつも受け入れてくれた。
妻が、寝たきりになったとき、老人は、妻の世話を運命として受け入れた。
妻への感謝の念や愛情からではなかった。老人は、そう考えた。
しかし、妻の身体を拭き、下着を取り替えてやり、食事をさせてやるという生活を続けるうちに、愛とは、若い頃に考えていたよりも、深く大きなものであることに気付き始めた。
いつの間にか、あたりはどっぷりと暮れている。
帰らなくちゃな。
俺には、待っている人がいる。
1995/09/16
太陽は、真上から照りつけているが、夏の激しさの変わりに、優しさを持っている。
老人の体は、軽く汗ばんでいる。風に冷たさを感じる。
見上げると、太陽は、西に傾いている。老人の長い影を、畑の上に作っている。
今日は、これまでだな。
老人は、腰を下ろし、タバコと携帯用の灰皿を取り出す。
タバコに火を点ける。タバコの煙が、夕焼けの空にゆっくりと昇っていく。
老人は、妻の身体を拭いていたとき、湯が天井に反射した、明るい陽光のことを思った。
あの光は、心を癒す光だ。
妻の背中には、大きな傷跡がある。
若い頃、老人の心は、荒れていた。
酔った老人は、恐ろしい勢いで妻を蹴飛ばした。その時の傷だった。
そんな老人を、妻は、なにも言わずにいつも受け入れてくれた。
妻が、寝たきりになったとき、老人は、妻の世話を運命として受け入れた。
妻への感謝の念や愛情からではなかった。老人は、そう考えた。
しかし、妻の身体を拭き、下着を取り替えてやり、食事をさせてやるという生活を続けるうちに、愛とは、若い頃に考えていたよりも、深く大きなものであることに気付き始めた。
いつの間にか、あたりはどっぷりと暮れている。
帰らなくちゃな。
俺には、待っている人がいる。
1995/09/16
桜花
義雄は、北鎌倉の駅で降りる。
陽射しは厳しいが、風が吹きわたり涼しい。
義雄は、鎌倉にある公園まで歩く。さすがに汗をかく。
桜花は、静かに横たわっていた。
日本帝国軍が開発した、有人ロケット弾。
義雄は汗を拭いながら、721海軍航空隊すなわち神雷部隊への募集が実施されたのも、こんな暑い日だったと気付いた。
神雷とは、桜花のことだった。
だから、募集といっても、それは、国家のために死ねという命令だった。
友が、応募した。
誰かが、行かなければならない。
義雄は、ただ何度も頷いただけだった。
トトト・ツー。神雷部隊が、無線を発する。攻撃突入。
その無線を発した後、神雷部隊は、完全な沈黙を守った。
後に人々は、その沈黙は、死を強いられた人間の精一杯の抵抗ではなかったかと話し合った。
けっきょく、神雷部隊は、沈黙のなかで、全滅した。
桜花は、ついに母機から発射されなかった。
友は、栄光の死も拒否されてしまった。
犬のように死んでいったのだ。
海風が、義雄と桜花の間を通り過ぎる。
義雄は、デイ・パックから写真を取り出す。
古く、空気に酸化され黄ばんだ写真。
義雄と友が、並んで写った写真。
まだ、20代の友は、屈託なく笑っている。
※桜花は、日本帝国軍が実際に開発した兵器です。
1995/09/14
陽射しは厳しいが、風が吹きわたり涼しい。
義雄は、鎌倉にある公園まで歩く。さすがに汗をかく。
桜花は、静かに横たわっていた。
日本帝国軍が開発した、有人ロケット弾。
義雄は汗を拭いながら、721海軍航空隊すなわち神雷部隊への募集が実施されたのも、こんな暑い日だったと気付いた。
神雷とは、桜花のことだった。
だから、募集といっても、それは、国家のために死ねという命令だった。
友が、応募した。
誰かが、行かなければならない。
義雄は、ただ何度も頷いただけだった。
トトト・ツー。神雷部隊が、無線を発する。攻撃突入。
その無線を発した後、神雷部隊は、完全な沈黙を守った。
後に人々は、その沈黙は、死を強いられた人間の精一杯の抵抗ではなかったかと話し合った。
けっきょく、神雷部隊は、沈黙のなかで、全滅した。
桜花は、ついに母機から発射されなかった。
友は、栄光の死も拒否されてしまった。
犬のように死んでいったのだ。
海風が、義雄と桜花の間を通り過ぎる。
義雄は、デイ・パックから写真を取り出す。
古く、空気に酸化され黄ばんだ写真。
義雄と友が、並んで写った写真。
まだ、20代の友は、屈託なく笑っている。
※桜花は、日本帝国軍が実際に開発した兵器です。
1995/09/14
2016/03/27
約束
突然の眩暈。
激しい勢いで、老人は畳みの上に、仰向けに倒れる。
それから、老人の1人住まいの家は、静まる。
太陽が、天空を横切り、空を赤く染めてから、沈む。
びっくりするほど大きな月が、昇る。
月光が、窓から老人の上に降り注ぐ。
老人は、目を開ける。しばらく月を見つめる。
そうか、俺は朝からこうしていたのか。
簡単な四則演算をしてみる。よし、頭には異常はないようだ。
老人は、身体を点検する。身体にも異常はない。
ゆっくりと起き上がろうとした。だめだ。何度か試みて、老人は諦めた。
そのまま、月の光りの中に、身を横たえる。
戸を叩く音。
誰だろう。戸が開けられる。
だめじゃないか、約束を破るなんて。澄んだ声がする。
月明かりの中に、ほっそりした少年の姿が浮かぶ。
おお、孝夫じゃないか。
老人は、懐かしさに涙を流しそうになる。
老人と孝夫は、池の話を聞いた。
満月の夜になると、月に誘われるようにして、大きな大きな魚が現われる。
老人と孝夫は、その魚を見に行こうと約束したのだった。
老人は、眠ってしまった。
孝夫は、1人で池に行き、溺れ死んだ。
孝夫、すまなかったなあ。
少年は、微笑みながら、首を横に振る。
ばかだなあ、今から行くんじゃないか。
孝夫は、手を差し出す。老人は、その手につかまる。
老人は、少年の姿に戻っている。
2人の少年が、月光の道を歩いていく。
1995/09/12
激しい勢いで、老人は畳みの上に、仰向けに倒れる。
それから、老人の1人住まいの家は、静まる。
太陽が、天空を横切り、空を赤く染めてから、沈む。
びっくりするほど大きな月が、昇る。
月光が、窓から老人の上に降り注ぐ。
老人は、目を開ける。しばらく月を見つめる。
そうか、俺は朝からこうしていたのか。
簡単な四則演算をしてみる。よし、頭には異常はないようだ。
老人は、身体を点検する。身体にも異常はない。
ゆっくりと起き上がろうとした。だめだ。何度か試みて、老人は諦めた。
そのまま、月の光りの中に、身を横たえる。
戸を叩く音。
誰だろう。戸が開けられる。
だめじゃないか、約束を破るなんて。澄んだ声がする。
月明かりの中に、ほっそりした少年の姿が浮かぶ。
おお、孝夫じゃないか。
老人は、懐かしさに涙を流しそうになる。
老人と孝夫は、池の話を聞いた。
満月の夜になると、月に誘われるようにして、大きな大きな魚が現われる。
老人と孝夫は、その魚を見に行こうと約束したのだった。
老人は、眠ってしまった。
孝夫は、1人で池に行き、溺れ死んだ。
孝夫、すまなかったなあ。
少年は、微笑みながら、首を横に振る。
ばかだなあ、今から行くんじゃないか。
孝夫は、手を差し出す。老人は、その手につかまる。
老人は、少年の姿に戻っている。
2人の少年が、月光の道を歩いていく。
1995/09/12
風
視界一杯に広がる、草原。強い風。
草原は、海のように、波うっている。
海面の下には、少年と少女が風を避けて潜っている。
女神よ、熱情の毒を塗った愛の矢をこの身には向けられますな。
少年の目が、悪戯っぽく輝く。
それって、私はさかりのついた猫になりたくないってことだろう。
少女は、溜息をつく。
君って、頭はいいけど、最悪ね。
少年は、ニャオと鳴いてみせる。
少年は、風の音に耳を澄ます。それから、話し始めた。
ほら、夢の中で、知った人に会うだろう。昔の人は、それは、その人が自分のことを思ってくれるからだと考えたんだ。素敵な考え方だと思うんだ。
まず「私」という存在があるんじゃなくて、人の思いが先にあるんだ。
夢は、「私」の思いが、創るんじゃなくて、人の思いが創るのさ。
少女は、それについて、しばらく考えてみる。
つまり、私たちは、生きているんじゃなくて、思いに生かされているのね。
少年は、にっこりと微笑む。
だから、君が好きさ。
ひときわ強い風が、草原を通り過ぎる。
風が、草に立てさせた音が、周りを包む。
それから、静寂が戻る。
2人は、なにか大きなものが、そっと触れて、立ち去ったのを感じた。
1995/09/09
草原は、海のように、波うっている。
海面の下には、少年と少女が風を避けて潜っている。
女神よ、熱情の毒を塗った愛の矢をこの身には向けられますな。
少年の目が、悪戯っぽく輝く。
それって、私はさかりのついた猫になりたくないってことだろう。
少女は、溜息をつく。
君って、頭はいいけど、最悪ね。
少年は、ニャオと鳴いてみせる。
少年は、風の音に耳を澄ます。それから、話し始めた。
ほら、夢の中で、知った人に会うだろう。昔の人は、それは、その人が自分のことを思ってくれるからだと考えたんだ。素敵な考え方だと思うんだ。
まず「私」という存在があるんじゃなくて、人の思いが先にあるんだ。
夢は、「私」の思いが、創るんじゃなくて、人の思いが創るのさ。
少女は、それについて、しばらく考えてみる。
つまり、私たちは、生きているんじゃなくて、思いに生かされているのね。
少年は、にっこりと微笑む。
だから、君が好きさ。
ひときわ強い風が、草原を通り過ぎる。
風が、草に立てさせた音が、周りを包む。
それから、静寂が戻る。
2人は、なにか大きなものが、そっと触れて、立ち去ったのを感じた。
1995/09/09
2016/03/24
視線
電車が、光りをまばゆく反射させながら、入線する。
ドアが開く。忠夫は、電車に乗る。
席が空いている。忠夫は、腰を下ろした。
背後から、初秋の陽光を受ける。不快でなく、心地いい。
夏去りぬか。
忠夫は、本を取り出し、読みはじめる。
視線を感じた。焼けるような、熱さを持った視線。
忠夫は、視線を動かさずに、周囲を窺う。相手を捉えることはできない。
軽く欠伸をしてみせながら、背後の窓を振り返る。
窓ガラスの反射の中に、視線の持ち主を探す。相手を捉える。40前後の男。
忠夫は、視線を本に戻す。
ページをめくりながら、男のイメージを、記憶の中にあるイメージと、1つ1つ照合していく。
忠夫の心の中で、3年前のぎらつく夏の太陽が甦った。
焼けついたアスファルトの道路。
忠夫は、犯人の取調べを、新米の部下に任せた。
一瞬の隙を見つけて、逃げだす犯人。口から血を流し、道路に仰向けになった部下。
忠夫は、犯人の背中と部下を見較べた。
忠夫は、犯人を追った。犯人との距離は、なかなか縮まらない。
忠夫の視界には、真夏の太陽と犯人の背中しかない。
咽喉が乾いたぜ。
その時、犯人が振り向いた。苦しそうな表情。
忠夫は、追い付けると確信した・・・あの時の男か。
電車が止まる。
視線の持ち主が、立ち上がる気配がする。そのまま、出ていった。
忠夫は、顔を上げる。空っぽの席があった。
夏去りぬ。
忠夫は、今度は、口にだして言ってみた。
1995/09/07
ドアが開く。忠夫は、電車に乗る。
席が空いている。忠夫は、腰を下ろした。
背後から、初秋の陽光を受ける。不快でなく、心地いい。
夏去りぬか。
忠夫は、本を取り出し、読みはじめる。
視線を感じた。焼けるような、熱さを持った視線。
忠夫は、視線を動かさずに、周囲を窺う。相手を捉えることはできない。
軽く欠伸をしてみせながら、背後の窓を振り返る。
窓ガラスの反射の中に、視線の持ち主を探す。相手を捉える。40前後の男。
忠夫は、視線を本に戻す。
ページをめくりながら、男のイメージを、記憶の中にあるイメージと、1つ1つ照合していく。
忠夫の心の中で、3年前のぎらつく夏の太陽が甦った。
焼けついたアスファルトの道路。
忠夫は、犯人の取調べを、新米の部下に任せた。
一瞬の隙を見つけて、逃げだす犯人。口から血を流し、道路に仰向けになった部下。
忠夫は、犯人の背中と部下を見較べた。
忠夫は、犯人を追った。犯人との距離は、なかなか縮まらない。
忠夫の視界には、真夏の太陽と犯人の背中しかない。
咽喉が乾いたぜ。
その時、犯人が振り向いた。苦しそうな表情。
忠夫は、追い付けると確信した・・・あの時の男か。
電車が止まる。
視線の持ち主が、立ち上がる気配がする。そのまま、出ていった。
忠夫は、顔を上げる。空っぽの席があった。
夏去りぬ。
忠夫は、今度は、口にだして言ってみた。
1995/09/07